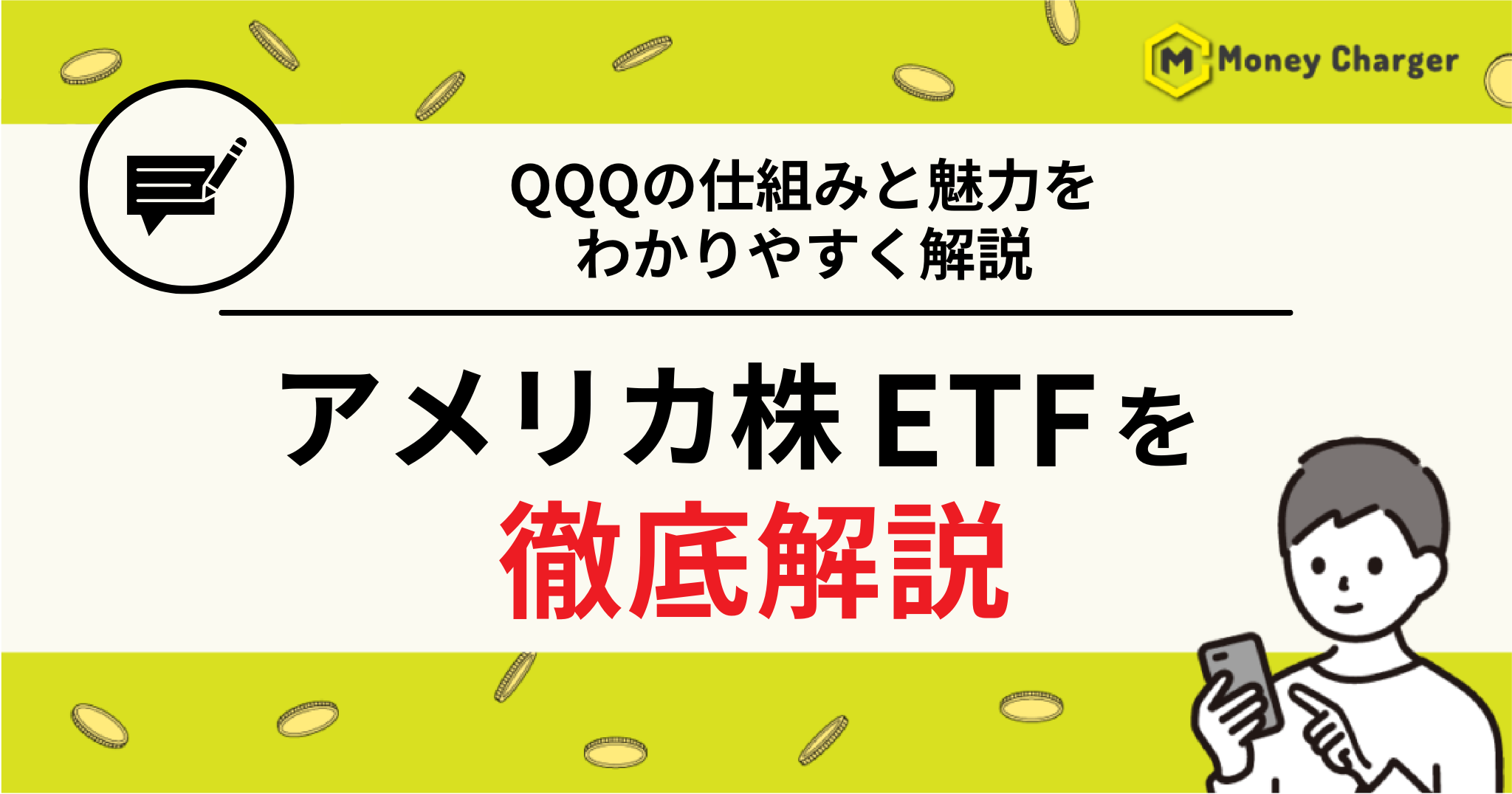先週金曜日に大阪で開催されたWebX Fintech EXPOで、パネリストたちは日本の進化するステーブルコインの状況について議論し、規制の進展と実際の採用の間のギャップを強調した。
参加者には、三井住友フィナンシャルグループの磯和昭夫氏、ProgmatのCEOである斎藤達也氏、サークルの日本マネージャーである坂木原健太氏が含まれ、DeFimansのCOO/CFOである坂上健太氏が司会を務めた。
日本と米国: ステーブルコイン規制の対照的なアプローチ
日本の金融セクターでは、法定通貨に1:1でペッグされたデジタル通貨であるステーブルコインへの関心が高まっている。8月19日、日本の金融庁は JPYC、国内初の円建てステーブルコイン を承認し、この秋に正式発行が予定されている。しかし、規制の監視は2022年から行われており、日本は先行者利益を得ている。
対照的に、米国のステーブルコインであるテザーのUSDTやサークルのUSDCは、連邦法が制定される前に広く採用された。 GENIUS法 は7月に議会で可決され、大統領が署名し、発行者に対する規制の枠組みを確立した。10億ドルを超える発行には連邦の監視が含まれ、USDCだけで670億ドルを発行し、通貨監督庁の管轄下にある。
サークルの坂木原氏は3つの重要な違いを強調した。
- 日本は2022年に先駆的なステーブルコイン規制を導入し、他国の参考となっている。
- 米国の法律は現在、大規模な発行を連邦の監督下に置いている。
- 取引の上限が異なり、日本では100万円に制限されており、米国とは大きく異なる。
磯和氏は、「米国では、テザーとサークルの合計発行額が30〜40兆円に達し、短期国債の利回りが高いことが要因」と述べた。また、マネーロンダリング対策の課題についても強調し、「銀行はAMLを管理しているが、ステーブルコインでは発行者が自らコンプライアンスを確保しなければならず、これは重要な問題である」と述べた。
ステーブルコイン提供者の課題
ProgmatのCEOである斎藤達也氏は、主要な日本の銀行と共同で設立したデジタル資産インフラのプラットフォームについて、運用上の課題を議論した。「プロバイダーが銀行か暗号資産関連企業かによって、規制の影響は微妙に異なる」と説明した。
彼はさらに、「小売取引は100万円を超えることはまれだが、企業や機関投資家向けの卸売取引を扱う銀行は、より厳しい規則に直面している。すべてのシナリオでコンプライアンスを確保することが課題である」と述べた。
市場の潜在力と世界的な波及効果
パネリストたちは、JPYCの発行が日本初の円建てステーブルコインとして重要なマイルストーンであることに同意した。坂木原氏はサークルの戦略を説明し、「3月末に日本でUSDCの運用を開始した。市場は卸売国際送金や財務運営をステーブルコインに移行するアイデアを共有している。円建てトークンへの強い需要があり、GENIUS法から日本のエコシステムへの好影響を期待している」と述べた。
日本のQRコードを用いたキャッシュレス決済の経験は、ステーブルコインの採用に影響を与える。磯和氏は、「当初、複数のQR決済システムが消費者の混乱を招いたが、相互運用性が向上した。ステーブルコインも同様の道をたどるだろう。どのトークンを採用するかの早期調整が重要である」と述べた。
彼はさらに、卸売銀行が内部ステーブルコインから利益を得る可能性について、「グローバル企業はキャッシュマネジメントシステムを通じて資金をプールしているが、時差が送金を遅らせている。ステーブルコインは即時の移動を可能にし、効率と労働生産性を向上させる」と述べた。
ステーブルコインのキャッシュレスシステムに対する利点
斎藤氏は技術的な利点を強調し、「現在のキャッシュレス決済は、商人のデータベースごとに分断されており、相互運用性がない。ステーブルコインは共通の標準に基づいて構築されており、異なるトークン間での容易な交換を可能にする」と述べた。
彼は市場の統合を予測し、「当初は複数のステーブルコインが出現するが、時間とともに収束するだろう」と述べた。斎藤氏は、「GENIUS法とJPYCの発行は、日本の金融セクターにとって 警鐘 である。今ステーブルコインを無視することは、関与することよりも大きなリスクを伴う」と結論付けた。